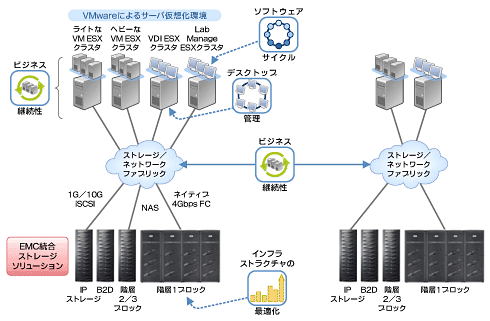| 多彩な最新ストレージ技術を提供 データセンターの消費電力削減を目指すEMC |
| データセンターでは、企業活動を支えるITインフラの設置場所として高度な信頼性や耐障害性が求められるのは当然だが、それに加えて現在では、高度な効率性も求められるようになってきている。信頼性を高めるためにはコストに糸目は付けない、などと言える状況ではなくなってきているのだ。データセンターに設置される機器の主役とも言えるサーバとストレージに関して、EMCは仮想化を初めとするさまざまな最新技術を導入することで高度な効率性を実現する。 |
| 電力消費から見るデータセンターを取り巻く環境 | ||
現在では、ITインフラに関しても“グリーン”や“エコ”が重要なキーワードとして注目されており、省電力化を求める声が高まっている。しかし、データセンターにおける電力消費は、以前から深刻な問題として認識されてきている。それはハードウェアコストの低下により下落傾向にあるシステムの初期投資よりも、運用時の電気料金が相対的にコスト高の要因として注目されるようになってきたからだ。
コスト面での懸念は以前よりもさらに深刻化しているとも言える。しかし、ITインフラの消費電力量削減は単純な「節電」という発想でまかなえるレベルではない。現在の企業活動はITなしにはあり得ないといって過言ではなく、節電のためにITシステムを止めるというわけにはいかない。ITシステムを稼働させれば電力は不可避的に消費されることになるので、無駄な電力を使わないという高効率化の方向に進む以外に道はないのが実情だ。
エコロジーという観点からは、「古い機器を大事に使い続ける」ことも大事だとされるが、IT機器に関してはこの方針は有用とはいえない。IT機器の陳腐化は早いため、古い機器の処理能力では需要をまかなえないという問題ももちろんあるし、古い機器は単位電力当たりの処理能力が低く、買い替えコストを考慮に入れても新しいシステムで仮想化などの技術を活用するほうが安くなる可能性が高いからだ。
| 仮想化技術の活用によるサーバの消費電力低減 | ||
電力効率を高める上で効果的な手段となるのが、仮想化の活用だ。現在注目を集めているサーバの仮想化では、サーバの台数を減らすことで直接的かつ大幅な消費電力削減が可能になる。
サーバの処理能力を完全に使い切った状態では処理の遅延などが起こりやすくなり、サービスレベルの低下に繋がる懸念があるため、通常はピーク処理量を踏まえたサイジングを行なう。このため、ピーク以外の通常時には、サーバは処理能力を余らせた状態で運用されることになる。この余った処理能力は、いわば必要な余裕分ではあるが、サーバの台数が多い場合には、未活用の処理能力も大きくなり、投資効率を引き下げてしまう。例えばVMware、マイクロソフト、EMCの2008年の調査によれば、一般的な企業ユーザーが所有するサーバで5〜15%、直接接続のストレージで20〜40%と使用率は低く、きわめて無駄が多い。一方、サーバの消費電力は、処理負荷に完全に比例するというわけではない。例えプロセッサがアイドル状態であっても、サーバを動作させておくために必要な電力消費はゼロにはならないため、サーバの台数が多い場合には、消費電力量も増えてしまう。仮想化を活用して複数台のサーバを少数に統合すれば、余裕分の処理能力を複数のサーバで共用することになり、利用効率が向上する。同時に、サーバの台数が減ることに伴う消費電力量の削減も実現するため、特に大規模なデータセンター環境では効率改善の効果も大きなものになる。
例えばEMCは、仮想化技術を使ったデータセンター統合により1357台のサーバを231台の物理サーバに置き換えたという。作業負荷は毎年70%のペースで増大している中でサーバ台数を20%以下に減らせることに成功したその効果は劇的だ。設置スペース、電力、冷却のコストを3年間で400万ドル以上削減できると同社は見込んでいる。
EMCが2004年にVMwareの買収完了を発表した際には、ストレージとサーバ仮想化の組み合わせの意味がすぐに理解されたとは言い難い面もあった。しかし、今ではその価値は明らかだろう。ストレージの仮想化はサーバの仮想化に先行して実用段階に入り、複数のストレージを仮想的に集約することでストレージ利用の効率化と運用管理負担の軽減を実現した。続いて実用化されたサーバの仮想化は、仮想化されたストレージと組み合わせることでその効果をさらに高めることが可能だ。分かりやすい例では、仮想化されたサーバを複数の物理ハードウェア間で移動することで高信頼のHAクラスタ構成にしたり、負荷状況に応じて最適なハードウェアを選択するために使われるVMotionといった技術は、複数の物理サーバ間で共有されたストレージがあってこその機能となる。
サーバの仮想化自体は、サーバ・ハードウェアごとに個別に搭載されたDAS型ストレージで運用することも可能だが、サーバ環境をハードウェアから独立させ、柔軟な運用を可能にするという仮想化のメリットを活用するためには、ネットワーク接続型のストレージを活用することが望ましい。VMwareではさまざまなストレージをサポートしているが、EMCのストレージは、両社の関係から言ってももっとも確実な組み合わせであり、双方のメリットを引き出しやすいと言えるだろう。
| EMCの統合ストレージソリューションと、VMwareのサーバ仮想化技術を組み合わせることで高い効率性と可用性を実現できる(クリックで拡大) |
| 最新のストレージ技術による効率改善 | ||
次にストレージを中心とした情報管理のインフラについて見ていこう。最新のストレージ・ハードウェアには独自の効率化技術が多数盛り込まれてきており、以前とはレベルの違う効率的な運用が可能になっている。EMCの最新ストレージでは、現時点で利用可能な高効率化技術が網羅的に実装されており、ユーザーの運用状況に合わせてもっとも適切な技術を選べるようになっている。
例えば、仮想プロビジョニング機能では、物理的なストレージ容量を超えるボリュームサイズを設定できる。これは、将来的なボリュームサイズの拡大を見越した対応に役立つ。例えば、現在のデータ容量は1TBだが、将来的には5TBまで拡大することが予想される、という場合に、物理的なストレージ容量は1TB分だけ用意しつつ、ボリュームサイズは5TBで確保する、ということができる。データ量の増加ペースに合わせて物理ストレージ容量を順次追加すればよく、しかも最初に5TBのボリュームを確保しているため、サーバやアプリケーションの側では設定変更などが一切発生しない。仮想プロビジョニングを利用すれば、すぐには必要ないリソースを最初に一括導入する無駄を避けられるため、投資効率が向上する。電力効率向上に関しては、必要のないディスク・ドライブを回転させておくことがなくなる、という形で無駄な電力消費を避けられる。
一方、ドライブの回転停止(スピンダウン)という機能も実装されており、アクセスのないディスク・ドライブの回転を止めて無駄な電力消費を避けることができる。仮想プロビジョニングとスピンダウンは、電力消費の削減という点だけで見ればどちらか一方が実装されていれば充分とも思えるが、ユーザーの使用状況に応じてどちらがより有効か、どちらの技術が利用しやすいか、という点が変わってくる。両方が実装されていれば、ユーザーがそれぞれ最適な技術を選択することができるし、さらに両方を組み合わせて使用する、ということも可能だ。
なお、スピンダウンに関しては、階層化のアプローチとの組み合わせが事実上必須となる。階層ストレージは、低コスト・大容量・低速なストレージと、高価だが高速なストレージという特性の異なる複数のストレージを組み合わせて、それぞれの特性に合ったデータを格納することでコスト・パフォーマンスを最適化するという考え方だ。EMCのストレージでは、筐体内に特性の異なるディスク・ドライブを混在させることで、単一の筐体内部で階層化ストレージを実現できる。スピンダウンでは、アクセスのないドライブの回転停止を行なうのだが、回転が停止しているドライブに対するアクセスが発生した場合には、レスポンスの悪化といった不利な状況が生じる。そのため、たまたまアクセスが途切れた、というドライブを止めてしまうのはリスクが高く、しばらくアクセスがないことが確実だと思われるドライブを選んで止めるほうがよい。この見極めを適切に行なうためには、データへのアクセス・パターンをある程度明確にできる階層化ストレージとの組み合わせが効果的なのである。
筐体内での階層化ストレージの実現は、電力消費の削減に直接的な効果をもたらす。EMCのデータによれば、データ量当たりの電力コストを比較すると、1TBのSATA IIドライブ(5400rpm)の電力コストは146GBのFCドライブ(15000rpm)の5分の1以下だという。(ここでいう電力コストは、これらのドライブを搭載したストレージの消費電力にデータセンター内の空調設備なども含めた運用上必要な電力のコストである)。アクセス速度が速いが消費電力量も多いドライブと、相対的には低速だが電力効率が高いドライブとが選択できるので、データの性格に応じたドライブを適切に選択することで電力消費とパフォーマンスのバランスを最適化できるのである。さらに、エンタープライズ・クラスの最新のストレージ・デバイスとしてSSDも利用可能になっている。I/O性能の高さで注目されるSSDだが、電力面での優位性も見逃せない。駆動部のないSSDは、IOPS当たりの消費電力がハードディスクに比べて98%も削減されるのだ。
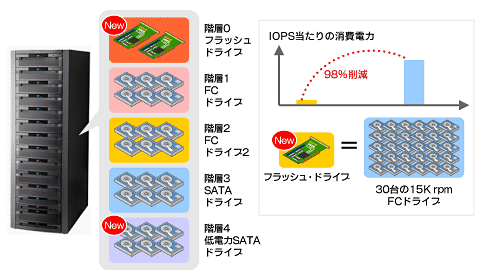
|
| 階層化ストレージの概念図。高速だが消費電力の大きなドライブと、それほど速くないが消費電力が小さいドライブを、データのアクセス頻度で使い分けることでパフォーマンスを維持したまま電力効率を上げられる。さらに速度、電力効率ともに優れたSSDという新たな選択肢も加わった |
| 高効率化のための情報を中心としたIT環境の全体最適化 | ||
ストレージでは、増加し続ける一方のデータ量に対応し、効率よく格納するための技術が次々と投入されているが、データ量の増加を抑制するための技術も登場してきている。EMC Avamarの重複排除は、データを可変長のデータ・セグメントに分解し、共通部分を集約することでデータ量そのものの増加を避ける技術だ。データ量の増加ペースを鈍らせることができれば、ストレージに要するコストやその運用に必要な電力消費削減など、そのメリットは大きい。
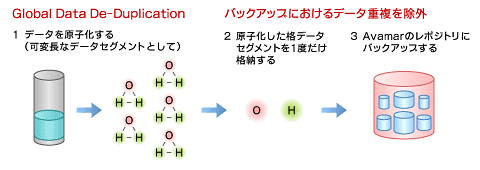
|
| データの重複除外の概念図。可変長なデータセグメントに分けて共通部分を集約することでデータ量を抑える |
EMCでは、単にストレージというデバイス・レベルの視点ではなく、データセンターなどの「情報インフラストラクチャ」全体の効率化を念頭に置いた全体最適化の実現に取り組んでいる。“情報”を中心に据え、情報に必要な保護を与えてセキュリティを維持しつつ、この情報を低コストで最大限に活用できる手段を提供していく、という考え方だ。ストレージ・デバイスに盛り込まれたさまざまな電力消費効率向上のための技術も、全体最適化に向けた取り組みの一環として位置づけられるものだ。
さらに、EMCではストレージ・デバイスのみに留まらず、上位層でのさまざまなソリューションをそろえており、組み合わせて利用することで情報インフラの全体最適化を実現することができるようになっている。一般的には、特定のシステム内部やソリューションごとと言った縦割りに細分化された最適化が行なわれがちだが、EMCではデータの格納場所であるストレージを出発点とし、データを中心にシステム横断的な最適化を実現している点が特徴となる。データセンターのような大規模な環境では、設置されるサーバやストレージといったハードウェアの数も多く、そこで扱われるデータの量も膨大になるため、ここで電力消費を効率化すればその効果も極めて大きなものになると期待できる。環境問題が社会的な課題として注目を集める現在、ITの効率化に関して、ユーザー企業自らも積極的に取り組むべき状況が出来上がりつつあるのではないだろうか。
| EMCのソリューション分類と製品名の概要(クリックで拡大) |
|
|
提供:EMCジャパン株式会社
企画:アイティメディア 営業本部
制作:@IT 編集部
掲載内容有効期限:2008年12月16日
ソリューションFLASH Pick UP!
クロネコデータセンター
ヤマトシステム開発
 ヤマトシステム開発は「クロネコヤマトの宅急便」で有名なヤマト運輸のコンピュータ部門に起源を持ち、ヤマトグループの ITシステムを30年以上に渡って支え続けてきた。全国にきめ細かなネットワークを持つヤマト運輸のITシステムへ求められる要件に応える過程で蓄積された、さまざまなノウハウを活かし、ユニークなサービスを展開する。
ヤマトシステム開発は「クロネコヤマトの宅急便」で有名なヤマト運輸のコンピュータ部門に起源を持ち、ヤマトグループの ITシステムを30年以上に渡って支え続けてきた。全国にきめ細かなネットワークを持つヤマト運輸のITシステムへ求められる要件に応える過程で蓄積された、さまざまなノウハウを活かし、ユニークなサービスを展開する。
Adaptec RAID 5シリーズ、2シリーズ
アダプテックジャパン
 2007年に「グリーンIT推進協議会」が設立されるなど、国内でもITの省エネ議論が活発になっている。しかし実はそれ以前から、商用データセンターや企業のデータセンターでは省電力が重要な課題だった。サーバやストレージの台数は増やさざるを得ないものの、データセンターでの電源供給には上限があり、その範囲内に納めるのが担当者にとっての頭痛の種だったのだ。ITの省電力については、これまでシステム全体で電力消費を抑えるというアプローチはあったが、それなりのコストを伴うことが導入の阻害要因となっていた。しかしアダプテックは、オープンな省電力技術により、「コストの掛からない省エネ」を実現する。
2007年に「グリーンIT推進協議会」が設立されるなど、国内でもITの省エネ議論が活発になっている。しかし実はそれ以前から、商用データセンターや企業のデータセンターでは省電力が重要な課題だった。サーバやストレージの台数は増やさざるを得ないものの、データセンターでの電源供給には上限があり、その範囲内に納めるのが担当者にとっての頭痛の種だったのだ。ITの省電力については、これまでシステム全体で電力消費を抑えるというアプローチはあったが、それなりのコストを伴うことが導入の阻害要因となっていた。しかしアダプテックは、オープンな省電力技術により、「コストの掛からない省エネ」を実現する。
最新ストレージ技術を活用した、データセンター省電力化アプローチ
EMCジャパン
 データセンターでは、企業活動を支えるITインフラの設置場所として高度な信頼性や耐障害性が求められるのは当然だが、それに加えて現在では、高度な効率性も求められるようになってきている。信頼性を高めるためにはコストに糸目は付けない、などと言える状況ではなくなってきているのだ。データセンターに設置される機器の主役とも言えるサーバとストレージに関して、EMCは仮想化を初めとするさまざまな最新技術を導入することで高度な効率性を実現する。
データセンターでは、企業活動を支えるITインフラの設置場所として高度な信頼性や耐障害性が求められるのは当然だが、それに加えて現在では、高度な効率性も求められるようになってきている。信頼性を高めるためにはコストに糸目は付けない、などと言える状況ではなくなってきているのだ。データセンターに設置される機器の主役とも言えるサーバとストレージに関して、EMCは仮想化を初めとするさまざまな最新技術を導入することで高度な効率性を実現する。
Veritas NetBackup 6.5 for VMware
シマンテック
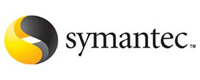 データセンターを検討するとき、もう仮想化を無視することはできないだろう。サーバ使用効率向上を狙える仮想化だが、物理サーバと同じバックアップ手法でいいのだろうか? シマンテックの答えは「NetBackup for VMware」にある。
データセンターを検討するとき、もう仮想化を無視することはできないだろう。サーバ使用効率向上を狙える仮想化だが、物理サーバと同じバックアップ手法でいいのだろうか? シマンテックの答えは「NetBackup for VMware」にある。
Veritas Storage Foundation
シマンテック
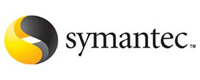 現在ではサーバの仮想化が注目を集めているが、技術の成熟度合いとしてはサーバの仮想化よりも「ストレージの仮想化」の方が先行している面がある。仮想化機能を備えたストレージハードウェアも各種販売されているが、機種ごとの機能がまちまちだったり、手持ちの古いストレージデバイスが取り残されてしまったりといった問題が生じる可能性もある。広範な種類のハードウェアをサポートできる、ソフトウェアによる仮想化のメリットに、あらためて注目が集まる。
現在ではサーバの仮想化が注目を集めているが、技術の成熟度合いとしてはサーバの仮想化よりも「ストレージの仮想化」の方が先行している面がある。仮想化機能を備えたストレージハードウェアも各種販売されているが、機種ごとの機能がまちまちだったり、手持ちの古いストレージデバイスが取り残されてしまったりといった問題が生じる可能性もある。広範な種類のハードウェアをサポートできる、ソフトウェアによる仮想化のメリットに、あらためて注目が集まる。
ホワイトペーパーダウンロード
そのバックアップシステム、万一のとき本当に事業を継続できますか?
事業継続計画(BCP)への取り組みは、今やあらゆる企業にとって避けて通れない課題だ。特に情報システムの観点では、効果的なデータバックアップ体制を構築できるかどうかが重要なポイントになる。
既存システムにあるHDDの消費電力を最大70%削減する手段
(グリーンITテクノロジーセミナー資料および技術文書)データセンターで稼働しているHDDは24時間365日、1つ1つが電力を消費し続けている。その消費電力や冷却コストは無視できない。それらを最大70%削減できる施策を紹介する。
データセンター移転/統合を最小限のリスクで実施するためにすべきこと
データセンター移転/統合やグリーン化など、次世代を見据えたデータセンターの構築を最小限のリスクで行うにはどうすればよいのか。
コスト削減とITガバナンス強化を同時実現! 情報インフラストラクチャ全体最適化
コスト削減とITガバナンスの強化を両立させるのは難しい。この2点を同時実現するためには情報インフラストラクチャの全体最適化を行うのが最も近道となる。
一筋縄ではいかない、VMware仮想化環境でのバックアップとリストア
いざサーバ仮想化技術を導入しても、仮想マシンのバックアップとリストアをどのように行えばいいのか、悩んでいる企業は多いのではないだろうか。本ホワイトペーパーでは、そのベストプラクティスを示す。
シンプロビジョニングを用いたストレージ戦略成功の秘策
シンプロビジョニングストレージを採用する企業が増えつつある。データセンターで運用タスクを単純化し、かつ設備投資を節約するためにどのような手段が必要となるのか。その秘策を紹介する。